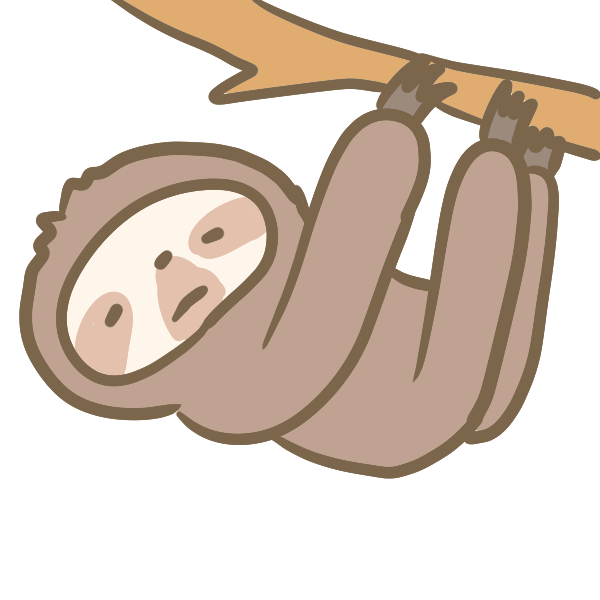ちょっと前に、「忖度」という言葉が流行しましたが、現代社会において、自分より上の立場の人に媚びへつらってしまう人は多いのではないでしょうか。
もしも、機嫌を損ねるようなことをしてしまうと自分の立場が危うくなりますからね。
しかし、今から約1200年前、今風に表現すると、上司や権力者に屈せず、真実を貫き通す、己の信念を貫き通す人物がいました。
今回は和気清麻呂(わけのきよまろ)という人物のお話です。
和気清麻呂ってどんな人?

和気清麻呂(わけのきよまろ)は、天平5(733)年に、備前国藤野郡(現:岡山県和気町)で郡司である父、乎麻呂のもとに生まれました。
清麻呂には、3つ上のお姉さんがいて、名前を広虫(ひろむし)といいます。この広虫も清麻呂を語る上では重要な人物なので覚えておいてください。
先に上京したのは姉の広虫(当時11歳)です。采女(うねめ)となって侍女として宮中に仕えます。地方豪族の子女が中央に派遣されて働くということはよくある話です。
仕えた人物はというと、阿倍内親王(あべのないしんのう)、後の孝謙(こうけん)・称徳(しょうとく)天皇です。
成人した弟の清麻呂も上京し、近衛府の武官となって朝廷に仕えます。
姉弟は、家財を共有するほど仲がよかったと言われています。
宇佐八幡宮信託事件

そんな都に、神護景雲3(769)年、「道鏡(どうきょう)を皇位につかせたならば天下は泰平である」との神託が奏上されます。もちろん、これは道鏡が自分が皇位につきたいがために仕向けた偽託です。
そんな道鏡を後押ししていたのが、称徳天皇(孝謙天皇が重祚)でした。
なぜ、称徳天皇が道鏡を後押ししていたのでしょうか?
それは、称徳天皇(当時孝謙上皇)が実母を亡くし、病に臥せっているときに、加持祈祷など献身的に道鏡が看病してくれたからでした。
回復してからは道鏡を重用し、さらに「法王」という地位を与えます。
称徳天皇は仏教を深く信仰し、道鏡への信頼はとても厚いものでした。
称徳天皇は、この神託を受けてとても喜びました。
確認するために法均(和気広虫)が派遣されるようになっていましたが、宇佐八幡宮までの長旅は耐えられないとのことで、代わりに派遣されたのが、和気清麻呂でした。
清麻呂は出発前に道鏡から「吉報を持ちかえれば官位を与える」と告げられました。
さぁ、このときあなたなら、どうするでしょうか??
忖度すれば、官位がもらえるんですから、自分にとってはプラスですよね。
しかし、清麻呂はそうはしませんでした。
「天皇には皇族のものが就くもの。道鏡は排除せよ」との神託を持ち帰ります。
これに称徳天皇は激怒。清麻呂は別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)、法均は別部狭虫売(わけべのせまむしめ)という卑しい意味の名前に変えられ、それぞれ大隅国と備後国に流罪になりました。
清麻呂が大隅国へ向かう途中、怒った道鏡は追ってを送り、襲わせます。
しかし、清麻呂は300頭ものイノシシに守られ、事なきを得たといいます。
この逸話から、清麻呂を祀る神社では、イノシシの像や絵があるんですね。

左遷されたのち
その後、光仁天皇が即位すると、清麻呂と広虫は許され、都に戻ることができました。従五位下に復位し、和気朝臣の姓が与えられました。
播磨国外介、豊前守に任命、さらに備前国、美作国の国造にも任命されるなどすっかり政界に復帰することができました。
一方、道鏡は下野国の薬師寺へ左遷され、静かにその人生を終えるのでした。
まとめ
いかがでしたか??
和気清麻呂が道鏡の神託を偽託とし、真実を貫き通したことはとても勇気のいる行為だったと思います。
自分の今いる立場を投げうってでも、真実を貫ける人というのは、なかなかいないんじゃないでしょうか。
和気清麻呂、すごい人だなぁ~
今回ご紹介した清麻呂の行動は、「忠臣の鏡」として戦前の歴史教育においてしばしば取り上げられていたようです。
確かに、視点を変えると清麻呂を上手く利用することもできますね・・・汗
時は流れて、明治にはなんとお札の肖像に描かれもしました。

歴史に「もし」はありませんが、もし道鏡を天皇にする旨の神託を持ち帰っていたなら、和気清麻呂は後世に名を残すことはなかったでしょう。
歴史もガラッと変わっちゃいますね(汗)
今回は和気清麻呂についてのご紹介でした。
姉の広虫の話もおもしろいので、興味のある方はしらべてみてください(記事にもできたらなと思います)。
最後までご覧いただきありがとうございました。
にほんブログ村ランキング
↓応援クリックよろしくお願いします!↓