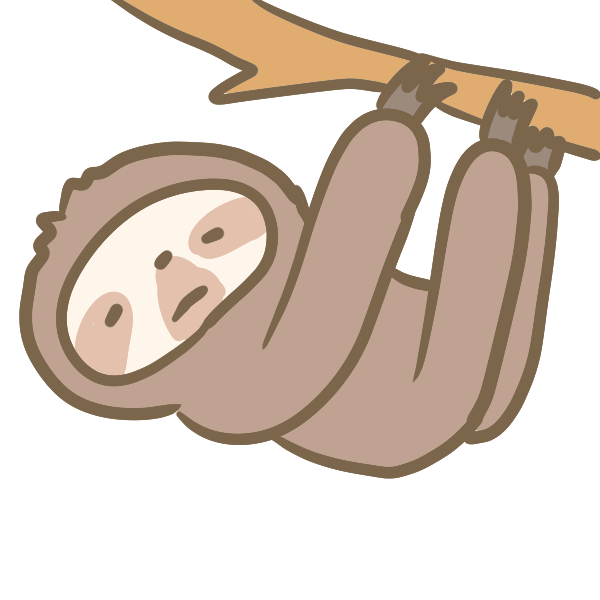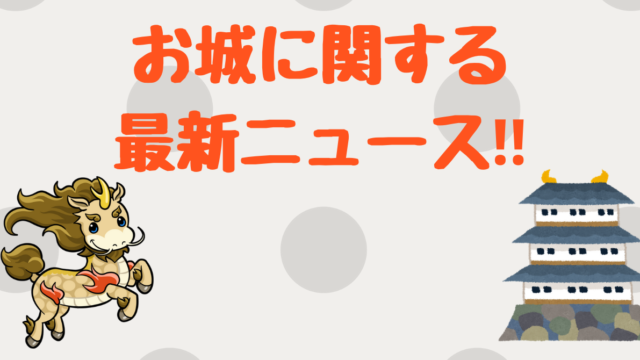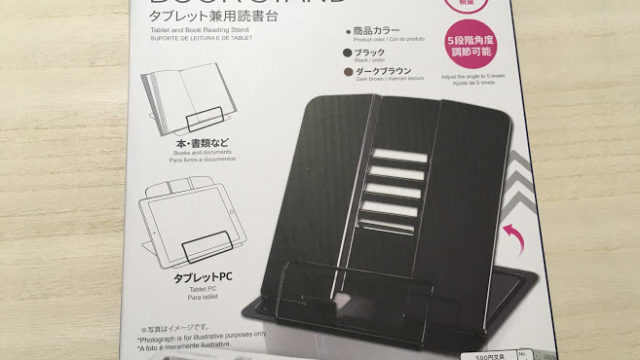ここでは日曜美術館で紹介されていた誰もが一度は見たことがある日本絵画5選についてまとめていきます。
1.「風神雷神図屛風」―俵屋宗達

まずは、俵屋宗達の『風神雷神図屛風』です。
本日の日曜美術館では、【愛され続けるキャラ誕生】という形で紹介されていました。
宗達は、近世初期の画家として知名度そして後世への影響はとても大きいのですが、その生涯については不明な点が多い人物です。
しかし、当時の一流文化人であった本阿弥光悦らとも交流があり、数多くの作品を生み出すなど、宗達自身も一流の絵師とみなされていたことは疑いありません。
それまでの人々にとって鬼は畏怖する存在であり、「雷」や「風」なども恐ろしいものでした。
しかし、宗達は、従来のイメージではなく善でも悪でもない中立の存在として描きました。『風神雷神図屛風』にある風神と雷神の表情に注目してみてください。
よーく見ると、笑っているように見えますね!
また、余白を広く取り、金箔で埋め尽くされています。豪快な構図も宗達ならではですね!
この余白が大切なんだということで、「要白」と言われたりもするそうです。
「雷」や「風」とともに生きる。そんな宗達の思いがうかがえる作品ではないでしょうか。
2.「紅白梅図屏風」―尾形光琳


尾形光琳は、京都の呉服商「雁金屋」の当主尾形宗謙の次男として生まれました。
光琳は生来の遊び人で、浪費の限りをつくし、親の遺産もあっという間に使い果たし、借金までかかえるありさま。借金返済のために絵師として活動していくことを決心します。
その中で、俵屋宗達の作品に触れ、彼を目標とし、さらには彼の作品に対抗し超えようと試みます!
そのようななかで創出されたのが、「紅白梅図屏風」でした。
番組では、【絵画とデザインの共演】と紹介されていました。
作品中央に位置する、独特な雰囲気を醸し出す水流は目を引きますよね。
これは、左右に梅を咲かせることで川の流れを際立たせる光琳によって考えられたデザインによるものです。
絵画を描いていく力と図を作っていく力を組み合わせた本当にすばらしい作品ですね!
3.「雪松図屛風」―円山応挙

円山応挙は、江戸時代中期から後期の絵師です。
応挙は、狩野派の画法や西洋画の透視的な写実法、さらには明や清の理想主義的な写実法を学び、それに日本画の装飾的表現法を融合させて独自の画法を作り出しました。
この『雪松図屛風』では、松を下から見るような形で描き、これまでの作品とはちがって、裏側を描くことによって二次元で三次元の空間を表現しています!
その他に『大瀑布図』では、滝を縦長に描いているのですが、下の方は床垂らすことによって滝つぼを表現するなど、本当に表現の仕方がすごいです。
4.「動植綵絵」―伊藤若冲

伊藤若冲は、江戸時代中期に京都・錦市場の青物問屋「桝源」の長男として生まれました。
若冲は、身の回りをつぶさに観察し、ありとあらゆる生き物を写生するスタイルをとりました。
『群鶏図』では、ひたすら写生を繰り返したとされる羽の表現に魅了されます。
黒と白と茶色を一筆単位で描いていくことで質感が表現されています。
芸術の才能も光るジャニーズグループ嵐の大野くんも「若冲の絵はムラがない!」と驚きの声を上げていました。
隅から隅まで手を抜くことなく描かれる若冲の絵画、ぜひ生で見てみたいですね。
5.「神奈川沖浪裏」―葛飾北斎

さいごは、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』です!
この絵は、日本だけでなく世界中でも大人気ですよね。
北斎は、宝暦10(1760)年に生まれ、江戸時代後期・化政文化を代表する浮世絵師です。
幼名は時太郎、のちに鉄蔵と称しました。
文化2(1805)年に、「葛飾北斎」の号を用いて活動します。
勝川春章に学び、狩野派や洋画などさまざまな画法を習得して、独自の画風を開きました。
風景版画『富嶽三十六景』などは、ヨーロッパ後期印象派の画家に影響を与え、ジャポニズム(日本熱)を生みました。
波の絵と言われて思い浮かべるのが、北斎の『神奈川沖浪裏』ですよね。
それも日本だけでなく世界中の人びとがそうというのだから、その影響力、魅力はすごいですね!
爪を立てて猛獣のように襲いかかってくる波と遠くに見える富士山がとても印象的です。
波は、大小の異なる弧ですべて描かれていて、とにかく波が立つ瞬間を描写しているところが非常におもしろいですよね。
「グレートウェーブ」とゴッホなど名だたる芸術家から呼ばれ称えられた作品であるのもうなずけます。
6.まとめ
いかがでしたか??
今回は、江戸時代を代表する日本絵画5選ということで、日曜美術館をもとにご紹介しました。
私自身も番組を見て、芸術の世界に魅了されてしまいました。
『風神雷神図屛風』や『紅白梅図屛風』を生で見た時のことも思い出されました。
もう一度見に行きたいですね~。また違った感じ方ができるような気がします。
それでは、このあたりで失礼いたします。
最後までご覧いただきありがとうございました。